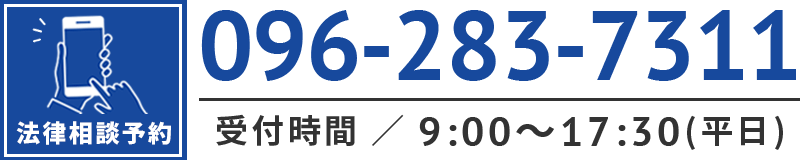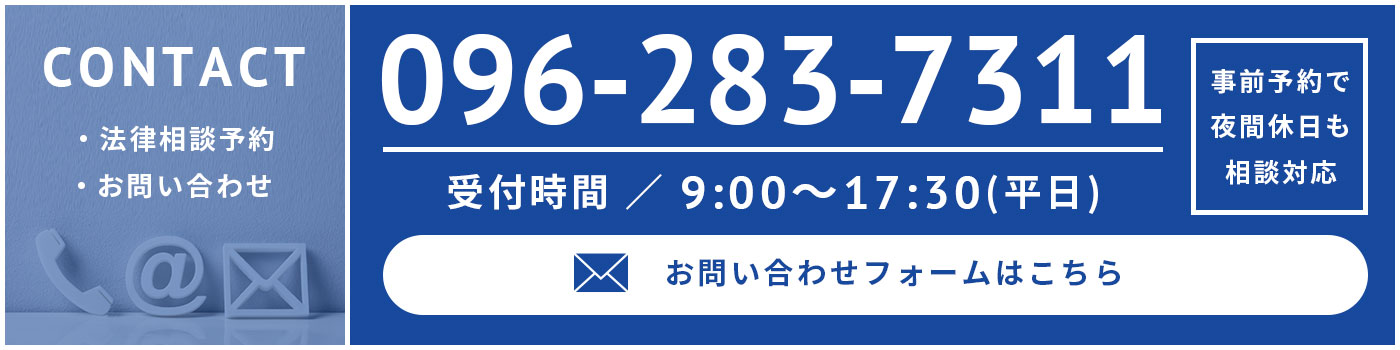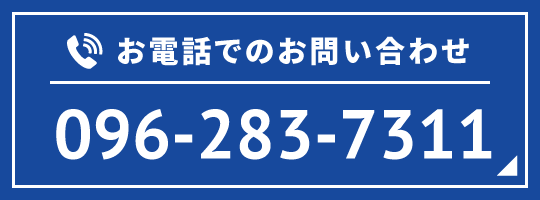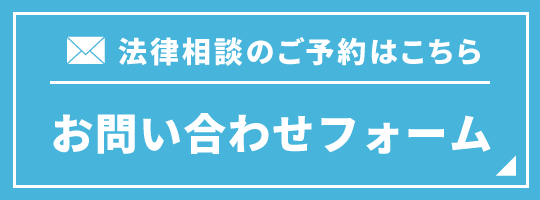刑事裁判は、検察官が起訴した事件について、被告人の有罪・無罪や刑罰の内容を判断するために行われる手続きです。刑事裁判がどのように進み、どの段階でどのようなことが行われるのかを把握することで、適切な準備が可能になります。
本記事では、刑事裁判の基本的な進行手順と、判決までの流れを解説します。
このページの目次
刑事裁判の基本的な流れ
刑事裁判は、以下の手順で進行します。
1. 起訴と裁判の開始
起訴の意味
- 検察官が被告人を起訴すると、裁判所が裁判の審理を始めます。
- 起訴には、公判請求と略式起訴があり、一般的にイメージされる裁判は公判請求のことです。
起訴状の送達
- 被告人に起訴状が送達され、事件の内容や罪名が通知されます。

2. 第一回公判
第一回公判では、裁判の方向性を決める重要な手続きが行われます。
冒頭手続き
- 人定質問
法廷に居る人物と起訴状に記載されている人物とが同一かを氏名、生年月日、住所、本籍地及び職業などで確認します。 - 起訴状の朗読
検察官が起訴状を朗読し、事件の内容を確認します。 - 罪状認否
被告人が起訴内容を認めるか否かを裁判官に伝えます。
・認める場合:量刑(刑罰の重さ)を判断する審理が進行します。
・否認する場合:検察側と弁護側が事件の事実関係を争う裁判となります。

3. 証拠調べ
証拠調べでは、検察側と弁護側がそれぞれの主張を裏付ける証拠を提出します。
検察側の証拠提示
- 物的証拠(凶器そのものなど)
- 書類証拠(供述調書、診断書など)
- 証人尋問
弁護側の反論
- 提示された証拠の正当性や信頼性を疑問視する。
- 弁護側独自の証拠を提示し、被告人に有利な状況を示す。

4. 証人尋問と被告人質問
証人尋問と被告人質問も事実の判断の材料となる証拠になります。
証人尋問
- 検察側と弁護側が、証人から事件に関する証言を得ます。
被告人質問
- 被告人が裁判官や検察官、弁護士から質問を受け、供述します。

5. 論告求刑と最終弁論
証拠調べが終了すると、検察官と弁護人がそれぞれの主張を最終的に述べます。
検察官の論告求刑
- 自白事件の場合には被告人にどのような刑罰を求めるか(求刑)を示します。
- 否認事件の場合には、何故検察官の主張する事実が認められるべきなのかを説明します。そのうえで、有罪となる場合の量刑についての意見を示します。
弁護人の最終弁論
- 自白事件の場合には被告人に有利な事情を主張し、刑罰の軽減や無罪を求めます。
- 否認事件の場合には、何故検察官の主張する事実が認められないのかということを説明します。検察官の主張する事実が認められないことから無罪や一部無罪などの主張をすることになります。
被告人の最終陳述
- 被告人が裁判官に対し、自らの意見や反省の意見を述べます。

6. 判決の言い渡し
裁判官が判決を下します。
判決内容
- 有罪の場合:懲役刑、罰金刑、執行猶予付き判決などが言い渡されます。
- 無罪の場合:被告人は釈放され、事件は終了します。
刑事裁判の種類
1. 地方裁判所での裁判
重大な犯罪(殺人、強盗など)や罰金以上の刑罰が予想される場合に行われます。
2. 簡易裁判所での裁判
軽微な犯罪(道交法違反、軽い窃盗など)が対象で、罰金刑が中心です。
3. 裁判員裁判
殺人や強盗致死などの重大な犯罪では、裁判員(一般の方)と裁判官が一緒に審理します。
判決後の対応
1. 控訴の検討
判決内容に不服がある場合、判決から14日以内に控訴を行うことができます。
控訴の理由
- 量刑が重すぎる場合。
- 事実について争っていたが、主張する事実と異なる事実認定がされた場合など。
2. 刑の執行
有罪判決が確定すると、刑が執行されます。
- 執行猶予付き判決:刑罰の執行は猶予され、一定期間中の再犯がなければ刑が免除されます。執行猶予期間中に再度犯罪を行わなければ刑務所に収監されることはありません。
再犯を行った場合には、再犯についての懲役刑と併せて執行猶予とされている懲役刑についても服役することになります。 - 実刑判決:懲役刑や罰金刑が執行されます。刑務所への収監や罰金の支払いがなされます。
裁判への対応策
1. 弁護士を依頼する
刑事裁判では、弁護士が被告人の権利を守り、公正な裁判を受けるためのサポートを行います。
弁護士の役割
- 証拠の精査と収集
- 証人尋問の準備と実施
- 被告人質問の指導
- 判決後の控訴手続きのアドバイス
2. 示談交渉を進める
被害者がいる事件では、示談を成立させることで量刑が軽減される可能性があります。
示談のメリット
- 被害者の被害感情が軽減される。
- 裁判官の心証が良くなり、執行猶予や軽い刑罰が期待できる。
3. 反省の姿勢を示す
罪を認める場合は、反省文の提出や更生プランの作成を通じて、誠意を示します。
刑事裁判の注意点
1. 供述の一貫性
裁判での供述が取り調べの内容と矛盾すると、不利な状況を招く可能性があります。
2. 証拠の重要性
提出された証拠が判決に大きく影響します。不利な証拠がないかを弁護士と確認し、適切に反論する必要があります。
3. 感情的にならない
裁判中の態度や発言が判決に影響を与える場合があります。冷静かつ誠実に対応することが大切です。
当事務所のサポート内容
当事務所では、刑事裁判における以下のサポートを提供しています。
提供サービス
- 公判での弁護活動:被告人の権利を守り、公正な審理を実現します。
- 証拠の収集と反論の準備:検察側の主張に対して、的確な反論を行います。
- 示談交渉の代理:被害者との示談を進め、量刑の軽減を目指します。
- 判決後の控訴支援:判決内容に不服がある場合の控訴手続きもサポートします。