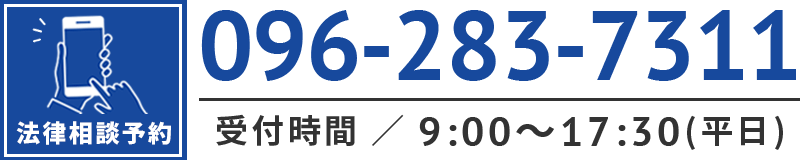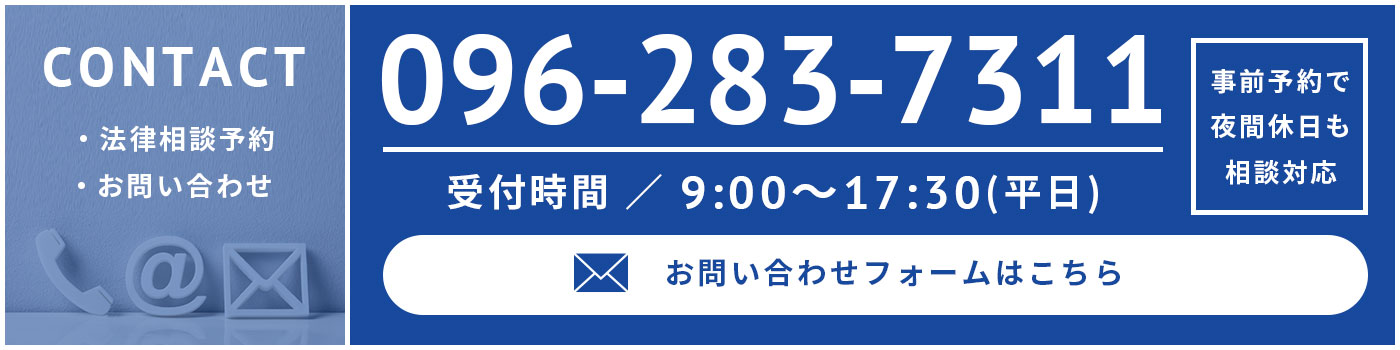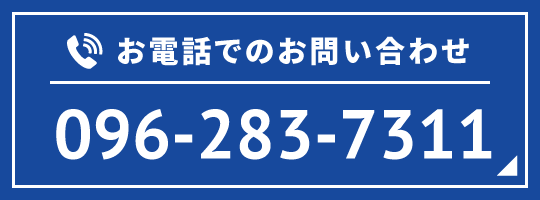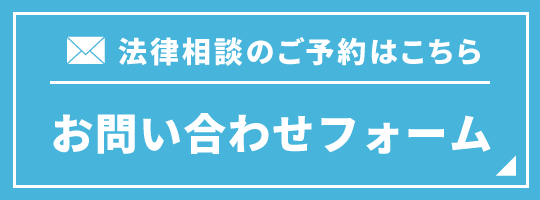離婚後、子どもの生活を支えるために支払われる養育費は、子どもの生活、教育、健康を維持する重要な費用です。養育費を適切に取り決めることで、子どもの生活が安定し、親同士のトラブルを防ぐことができます。
本記事では、養育費の計算方法や支払い義務について詳しく解説します。
このページの目次
養育費とは?
養育費は、離婚後に親権を持たない親が親権者に支払う子どもの養育にかかる費用を指します。
養育費の主な目的
- 子どもの衣食住、教育費、医療費などを支える。
- 離婚後も親としての責任を分担する。
養育費の支払い期間
- 原則:子どもが20歳になるまで。これまでは、成人年齢が20歳でしたので、20歳が終期とされているケースが多かったですが、成人年齢の引き下げに伴い終期を18歳(18歳となった次の3月=現役での高校卒業まで)とするケースが増えてきています。
- 例外:子どもが大学に進学する場合、22歳頃まで延長されることもあります(話し合い次第。)
養育費の計算方法
養育費は、夫婦双方の収入を基に、家庭裁判所が公表している標準算定方式、標準算定表を参考に計算されます。
1. 養育費算定表の基準
養育費算定表は、以下の要素を基に金額を算定します。
- 両親の年収(給与所得・自営業所得)
- 子どもの人数
- 子どもの年齢
2.個別事情による調整
以下の事情によって、標準算定方式などにより算出された金額が調整されることがあります。
- 子どもの特別な事情:病気や障害がある場合、教育費が高額になる場合など。
- 親の経済状況:支払う側の経済的困窮が深刻な場合、減額されることも。
養育費の支払い義務
1. 支払義務者
養育費は親としての責任であるため、子どもを監護しない親が支払う義務を負います。
2. 義務の免除は原則不可
養育費は子どものための費用であり、親の合意や経済状況によって一方的に免除されるものではありません。
3. 支払いの方法
養育費は通常、以下の方法で支払われます。
- 定期払い:毎月一定額を支払う(最も一般的)。
- 一括払い:将来の養育費をまとめて支払う(話し合い次第)。
4. 支払いの終了時期
原則として、以下のタイミングで支払い義務が終了します。
- 子どもが合意した終期に達したとき。
- 子どもが就労するなどして経済的に自立したとき。
養育費に関するトラブルと対策
1. 支払いの未履行
養育費の支払いが滞るケースは少なくありません。
主な対策
- 公正証書の作成
養育費の取り決めを公正証書にすると、支払いが滞った場合に強制執行が可能になります。 - 家庭裁判所への申し立て
養育費が調停等により定められた場合には支払いが止まった場合、履行勧告や強制執行を申し立てることができます。
2. 減額請求
支払う側の経済状況が悪化した場合、養育費の減額を申し立てることができます。
減額が認められる例
- 病気やケガによる収入減少。
- 失業や倒産。
3. 増額請求
逆に、子どもの生活状況が大きく変わった場合、増額を求めることも可能です。
増額が認められる例
- 子どもの医療費や教育費が急増した場合。
- 親権者の収入が大幅に減少した場合。
養育費取り決めのポイント
1. 具体的な金額と支払い方法を明記
養育費の金額、支払日、支払い方法を取り決め、文書に残します。
2. 公正証書の作成
公正証書を作成することで、トラブルが発生した際の強制執行が可能になります。
3. 家庭裁判所での調停
話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所で調停を申し立てることで公平な取り決めができます。
弁護士に依頼するメリット
1. 適切な金額の算定
弁護士が標準算定方式や家庭の状況を基に適切な金額を算定します。
2. 取り決め文書の作成
法的効力のある合意書や公正証書の作成をサポートします。
3. 支払い未履行時の対応
支払いが滞った場合、履行勧告や強制執行手続きの代行を行います。
4. 減額・増額請求のサポート
支払い金額に関する変更が必要な場合、調停や裁判で適切な主張を行います。
当事務所のサポート内容
当事務所では、養育費に関する以下のサービスを提供しています。
提供サービス
- 養育費の金額算定と交渉支援:法律や家庭の状況を基に、適切な養育費の金額を算定し、交渉をサポートします。
- 公正証書の作成:養育費の支払いを確保するための文書作成を代行します。
- 未払い養育費の回収:履行勧告や強制執行を通じて、未払い分の回収を支援します。
- 増額・減額請求の対応:養育費の金額変更が必要な場合の調停や裁判をサポートします。