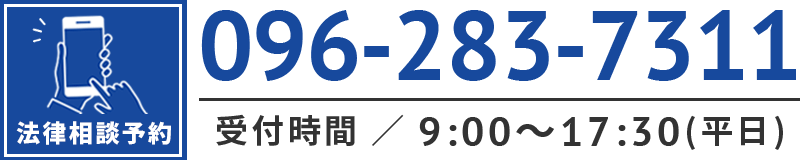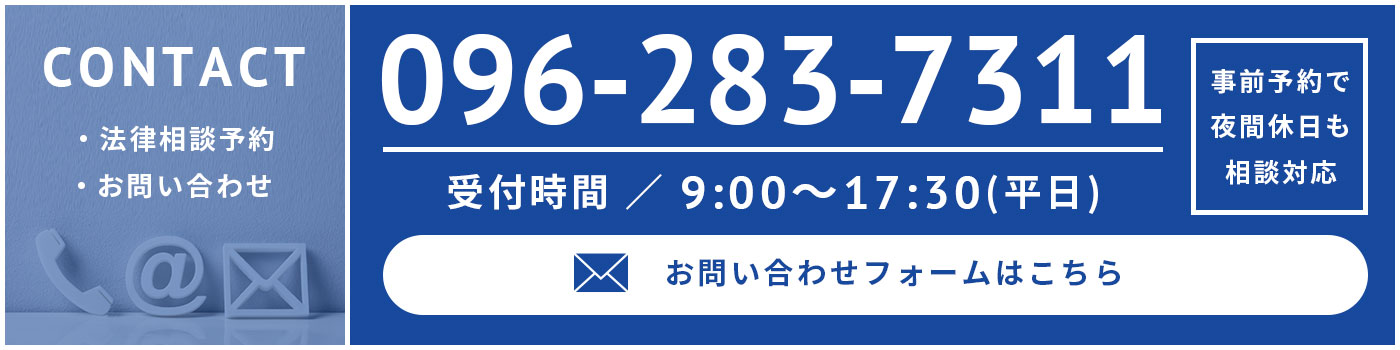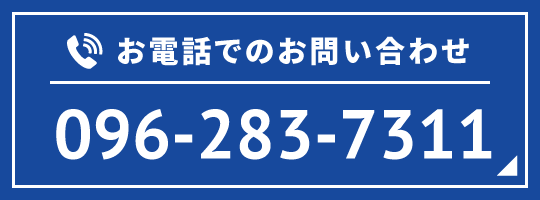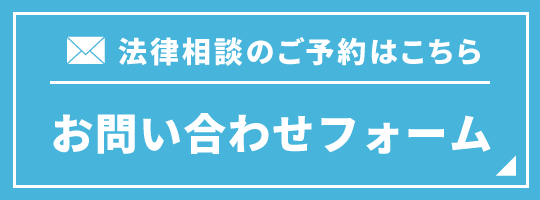インターネット上での誹謗中傷や風評被害は、個人や企業の名誉や信用を損なう深刻な問題です。SNSや掲示板、口コミサイトなど匿名性が高い環境では、被害が拡大しやすく、放置することでさらなる損害を招く恐れがあります。
本記事では、ネット上での誹謗中傷・風評被害に対する法的対応、被害を防ぐためのリスク管理、弁護士の役割について解説します。
このページの目次
1. ネット上の誹謗中傷・風評被害の現状
1. 誹謗中傷の具体例
- 個人の場合:SNSでの悪口や侮辱、プライバシーの暴露。
- 企業の場合:虚偽の口コミやレビュー、不正確な情報の拡散。
2. 主な影響
- 名誉毀損:社会的評価が低下し、信用を損なう。
- 業績悪化:風評被害が原因で顧客や取引先を失う。
- 精神的苦痛:個人が心理的ストレスを受ける。
2. 法的対応
ネット上の誹謗中傷や風評被害に対しては、速やかに法的手段を講じることが重要です。
1. 名誉毀損(刑法第230条、民法第709条)
法的要件
- 公然性:不特定多数に公開されていること。
- 具体性:事実関係が特定でき、名誉を毀損する内容であること。
- 名誉棄損性:社会的評価を低下させるおそれのある行為であること
名誉棄損行為の内容の真偽は問われません。事実であろうと虚偽であろうと名誉棄損が成立する可能性があります。
法的手続き
- 被害を証明し、損害賠償請求や刑事告訴を行う。
2. 侮辱罪(刑法第231条)
法的要件
- 具体的な事実を示さず、抽象的な悪口や侮辱的表現がなされたこと。
法的手続き
- 損害賠償請求や刑事告訴を検討
3. プライバシー侵害(民法第709条)
法的要件
- 個人の私生活情報を無断で公開し、本人に不利益をもたらす。
法的手続き
- 情報の削除請求や損害賠償請求を行う。
4. 業務妨害(刑法第233条)
法的要件
- 偽計(虚偽の情報の流布など)や威力(相手の意思を制圧する程度の強い威勢を示すことなど)、電気計算機損壊等(コンピューター本体・データの損壊・虚偽データなどによりコンピューターに目的に沿った動作をさせないまたは目的に反する動作をさせることなど)によって業務が妨害された場合。
法的手続き
- 刑事告訴を行い、拡散を防止。
3. 対応の流れ
1. 証拠の保存
- 問題の投稿やコメントをスクリーンショットで保存。
- 日時やURLを記録しておく。

2. プラットフォームへの削除依頼
- サイト運営者やSNSの管理者に対し、投稿の削除を依頼。
- 削除依頼フォームや通報機能を活用。

3. 発信者情報の開示請求
- 匿名の投稿者を特定するために、発信者情報開示請求を行う。
・対象:プロバイダーや通信事業者。
・手続き:裁判所に開示請求の申し立て。

4. 損害賠償請求
- 誹謗中傷の発信者に対し、損害賠償を請求。
- 精神的苦痛に対する慰謝料や、営業損害の賠償を求める。

5. 刑事告訴
- 特に悪質なケースでは警察に告訴し、刑事手続きを進める。
4. 被害を未然に防ぐリスク管理
1. ネットパトロールの実施
- 専門ツールやサービスを利用して、インターネット上の風評や誹謗中傷を監視。
2. 情報セキュリティ対策
- 顧客情報や従業員情報が漏洩しないように管理体制を強化。
3. 危機管理マニュアルの整備
- 誹謗中傷が発生した場合の対応手順をマニュアル化。
- 被害発生時に迅速な対応が可能となる。
4. 企業としての透明性を確保
- 誤解を招く可能性がある情報を適時適切に公開し、トラブルを未然に防ぐ。
5. 法的対応を見据えた専門家の活用
- 弁護士やIT専門家と連携し、早期に問題を解決。
5. 弁護士に依頼するメリット
1. 削除請求の迅速化
- サイト運営者やプロバイダーに対して、法的根拠に基づいた削除請求を行う。
2. 発信者情報の特定
- 発信者情報開示請求の手続きをサポートし、加害者を特定。
3. 損害賠償請求の代理
- 被害の程度に応じて適切な損害賠償を求め、和解交渉や裁判を代理。
4. 刑事手続きのサポート
- 特に悪質な誹謗中傷について、警察への告訴を支援。
5. 企業イメージの保全
- 風評被害を最小限に抑え、ブランド価値の維持をサポート。
当事務所のサポート内容
提供サービス
- 誹謗中傷の削除請求
投稿削除やサイトブロックの迅速な対応。 - 発信者情報開示請求
投稿者を特定し、必要な法的手続きを進めます。 - 損害賠償請求
個人や企業の損害を回復するための賠償請求を代理。 - 刑事手続きの対応
警察や検察との連携を支援。 - ネットパトロールの導入支援
企業や個人向けの監視体制構築をサポート。 - 危機管理マニュアルの作成
ネット上のトラブル発生時に迅速に対応できるマニュアルを作成。