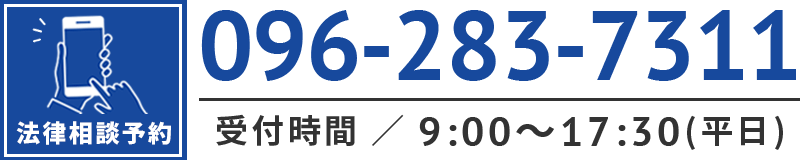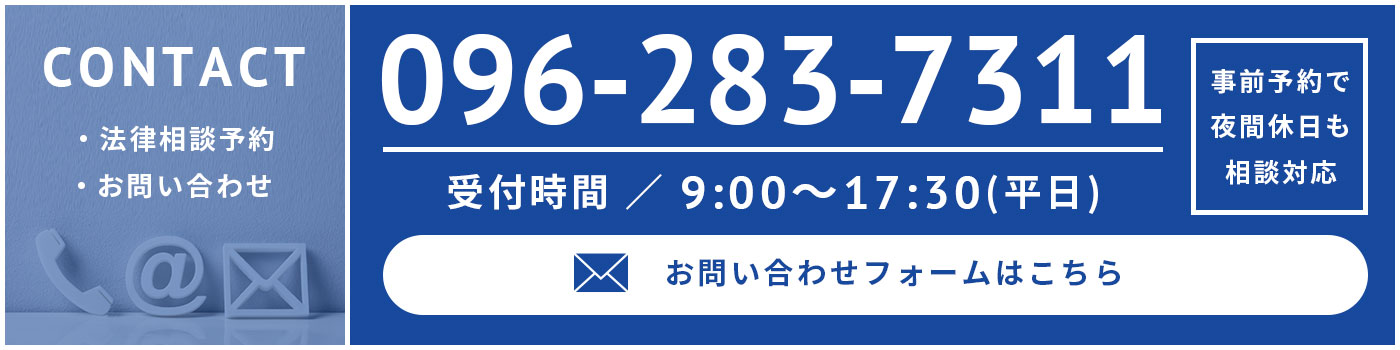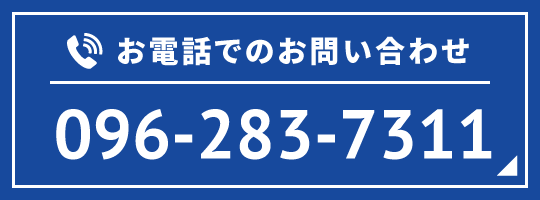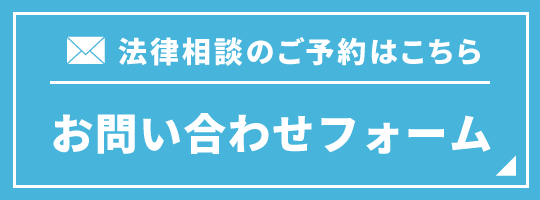遺留分とは、法定相続人が最低限受け取ることが保証されている遺産の割合を指します。これは、遺言書によって特定の相続人にすべての財産を譲る内容が記載されていた場合でも、一定の法定相続人が財産を受け取る権利を守るための制度です。
本記事では、遺留分の基本や請求方法、注意点について解説します。
このページの目次
遺留分とは?
遺留分は、相続人が最低限の遺産を確保するための権利です。遺留分を請求できる権利を「遺留分権利」と呼び、特定の相続人がこの権利を行使することで遺留分を取り戻すことができます。
遺留分の目的
- 家族の生活保障
特定の相続人が遺産を独占することで、他の相続人が生活に困窮することを防ぐ。 - 財産の公平な分配
家族間での大きな不平等を是正し、トラブルを防止する。
遺留分の対象となる相続人
遺留分を持つことができるのは、以下の法定相続人に限られます。
遺留分を持つ相続人
- 配偶者
- 子(直系卑属:子、孫など)
- 直系尊属(父母、祖父母など)
遺留分を持たない相続人
- 兄弟姉妹およびその子(甥・姪)
兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合
遺留分の割合は、法定相続分に基づいて以下のように定められています。
遺留分の計算方法
- 相続人が配偶者や子の場合
遺産全体の1/2が遺留分の対象。 - 相続人が直系尊属(父母など)のみの場合
遺産全体の1/3が遺留分の対象。
具体例
被相続人が遺産4,000万円を残して亡くなり、相続人が配偶者と子2人の場合
- 遺留分の割合:遺産の1/2 → 4,000万円 × 1/2 = 2,000万円
- 各相続人の遺留分:2,000万円を法定相続分で分配
・配偶者:1/2 → 1,000万円
・子1人あたり:1/4 → 500万円
遺留分侵害額請求
遺留分は自動的に守られるわけではありません。遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求」を行い、侵害された分の金銭を請求する必要があります。
遺留分侵害額請求の流れ
- 遺留分が侵害されているか確認
遺産の内容や分配状況を調査し、遺留分が侵害されているか確認します。 - 請求内容を通知
遺留分を侵害している相続人や受遺者(遺言によって財産を受け取った人)に対し、書面で請求内容を通知します。 - 話し合いによる解決
請求後、当事者同士で話し合いを行い、金銭の支払い方法などを決定します。 - 訴訟による請求(合意に至らない場合)
話し合いがまとまらない場合、地方裁判所または簡易裁判所に訴訟を提起して解決を図ります。
遺留分請求の期限
遺留分侵害額請求には期限があります。以下のいずれか早い方が適用されます。
- 遺留分の侵害を知った日から1年以内
- 相続開始から10年以内
期限を過ぎると、遺留分を請求する権利は消滅します。
遺留分に関連する注意点
1. 遺留分侵害額請求は金銭で行う
遺留分の請求は、遺産そのものではなく、金銭で行うのが原則です。たとえば、土地や不動産を遺贈された場合、その物件を返還するのではなく、相当額の金銭を支払うことになります。
2. 遺留分を放棄することも可能
相続開始前に遺留分を放棄することは可能です。ただし、この場合、家庭裁判所の許可が必要です。
3. 生前贈与も遺留分の対象になる
被相続人が生前に行った贈与(例:多額の現金や不動産の贈与)も、遺留分の計算に含まれることがあります。これを「特別受益」と呼びます。
遺留分トラブルを未然に防ぐ方法
遺留分を巡るトラブルを防ぐには、被相続人が生前に適切な対策を講じることが重要です。
1. 遺言書の作成
遺留分を考慮した内容の遺言書を作成することで、相続人間の争いを未然に防ぐことができます。
2. 生前贈与の計画
遺留分を考慮した生前贈与を計画的に行うことで、相続時のトラブルを減らせます。
3. 専門家への相談
相続に詳しい弁護士や税理士に相談することで、遺留分に関する適切なアドバイスを受けることができます。
当事務所のサポート内容
当事務所では、遺留分に関するトラブルの解決や未然防止に向けた支援を提供しています。
提供サービス
- 遺留分侵害額請求のサポート:請求手続きの代行や交渉の支援。
- 遺言書作成のサポート:遺留分を考慮した遺言書の作成支援。
- 生前贈与のアドバイス:相続トラブルを防ぐ贈与計画の立案。
- 相続人間の調整:公平で円満な解決を目指したサポート。