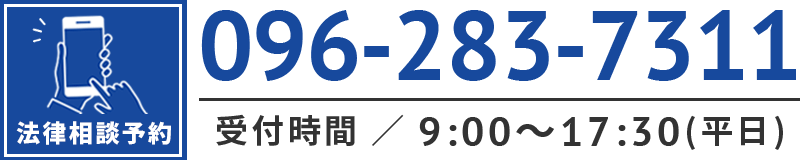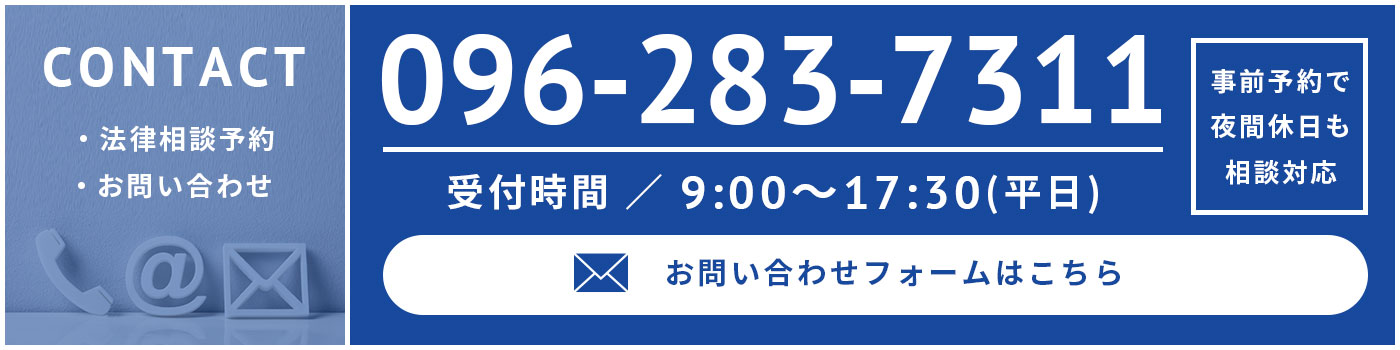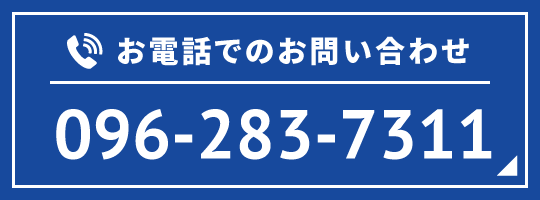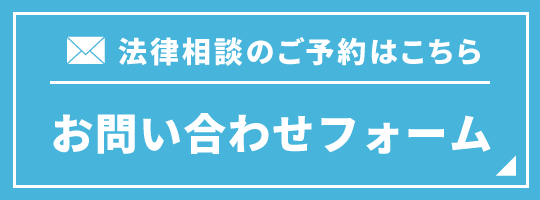交通事故による後遺症があるにもかかわらず、後遺障害等級が認められなかった場合や、認定された等級が低い場合、適切な補償を受けるためには迅速かつ的確に対応することが重要です。
本記事では、後遺障害認定が認められなかった場合の具体的な対応策を解説します
このページの目次
後遺障害認定が認められなかった理由の確認
まず、認定が認められなかった理由を正確に把握することが必要です。認定結果には理由が記載されており、以下の点が判断の基準になります。
主な理由
- 医学的根拠が不足している
・後遺障害診断書に具体的な記載がない。
・レントゲンやMRIなどの画像資料で異常が確認できない。 - 後遺障害が日常生活や労働能力に与える影響が不明確
後遺症の程度が軽微であると判断された。 - 因果関係が不明確
交通事故と後遺症との因果関係が認められなかった。 - 治療が完了していない(症状固定に至っていない)
症状固定と認められず、治療の継続が必要と判断された。
認定が認められなかった場合の対応策
1. 異議申立てを行う
後遺障害等級の認定に不服がある場合、損害保険料率算出機構に対して異議申立てを行い、再審査を求めることができます。
異議申立ての流れ
認定結果通知書を確認
認定が否定された理由を把握します。
追加資料を準備
必要に応じて、次の資料を用意します:
- 主治医による補足診断書
- 他の医療機関でのセカンドオピニオン
- MRIやCTスキャンなどの追加画像資料
保険会社または損保料率機構に提出
新たな証拠を添えて異議申立書を提出します。
再審査
損保料率機構が提出資料を基に再度審査を行います。
注意点
- 再審査でも結果が変わらない場合があります。
- 異議申立ては、初回認定の通知後3年以内に行う必要があります。
2. 医師に診断書の追記を依頼する
認定結果が不利な場合、診断書の内容に不備がある可能性があります。主治医に診断書の追記や再作成を依頼しましょう。
診断書作成時のポイント
- 後遺症の症状や日常生活への影響を具体的に記載してもらう。
- レントゲンやMRIの所見を明確に記載してもらう。
- 症状固定の時期や治療経過を詳しく説明してもらう。
3. 別の医療機関でセカンドオピニオンを受ける
主治医の診断書や意見書だけでは十分な証拠にならない場合、別の医療機関での診察を受け、新たな診断書を用意することが有効です。
セカンドオピニオンのメリット
- 客観的な視点から後遺症を評価してもらえる。
- 初回の診断と異なる意見が得られる場合がある。
4. 訴訟で争う
異議申立てでも納得のいく結果が得られない場合、訴訟を提起することが可能です。
訴訟の流れ
- 弁護士に相談し、認定結果を争う訴訟を提起します。
- 裁判所が後遺障害等級の適正性を判断します。
- 裁判所の判断に基づき、適正な補償額を請求します。
訴訟のポイント
- 弁護士の支援を受けることで、裁判基準に基づく適切な等級認定を主張できます。
- 訴訟には時間と費用がかかるため、メリットとデメリットを慎重に検討する必要があります。
5. 弁護士に相談する
後遺障害認定に関する手続きは専門知識が必要です。弁護士に依頼することで、適切な資料の準備や申請手続きを効率的に進めることができます。
弁護士が提供できるサポート
- 認定に必要な診断書や証拠資料のチェック
- 医療機関との連携や意見書の取得
- 異議申立てや訴訟手続きの代理
- 保険会社との交渉を有利に進める
後遺障害認定が否定されやすいケースと防止策
否定されやすいケース
- 症状が軽微であると判断された。
- 医学的根拠が不足している(画像検査で異常が確認できない)。
- 主治医の診断書が不十分。
防止策
- 初回の申請時から適切な資料を用意する。
- 主治医との十分なコミュニケーションを図る。
- 弁護士や専門家に手続きのサポートを依頼する。
当事務所のサポート内容
当事務所では、後遺障害認定が認められなかった場合の対応に特化したサポートを提供しています。
提供サービス
- 異議申立ての代理:必要な書類の準備や手続きを全面的に代行します。
- 診断書や意見書の内容確認:医師との連携を通じて、後遺症の状況が正確に反映された診断書を作成します。
- セカンドオピニオンの手配:信頼できる医療機関をご紹介し、適切な診断をサポートします。
- 訴訟手続きの代理:最終的に裁判で争う場合も、専門的なサポートを提供します。