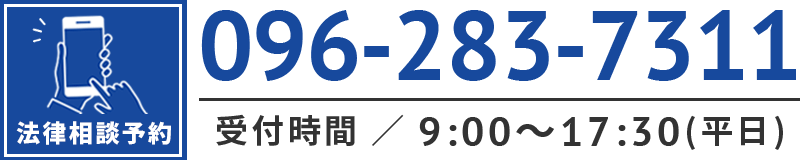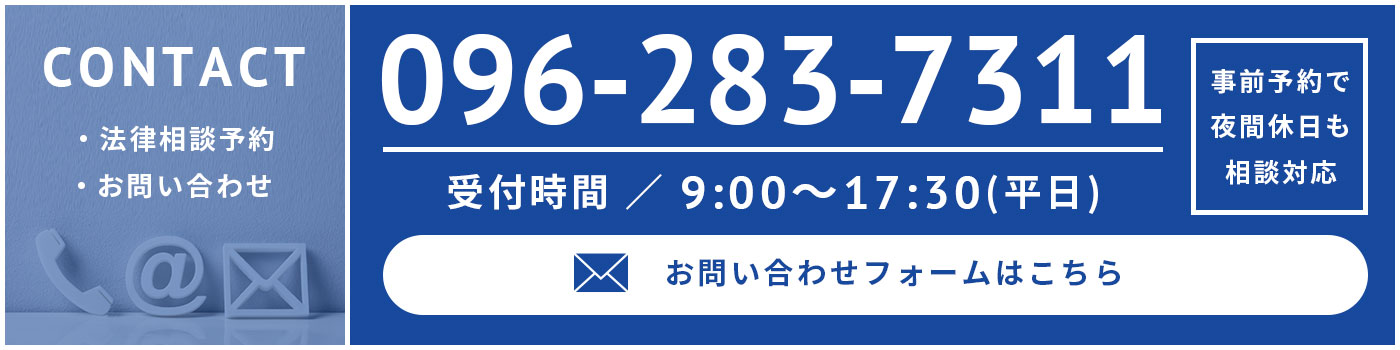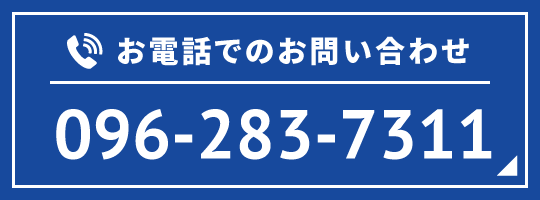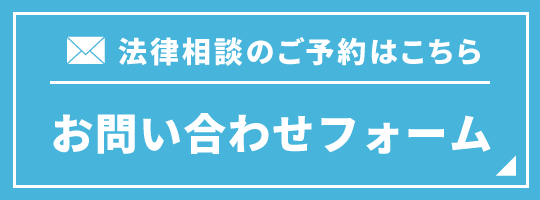相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切引き継がないことを選択する手続きです。主に被相続人が多額の負債を残している場合に検討されることが多いですが、その選択には一定の手続きやリスクも伴います。
ここでは、相続放棄の基本的な手続きと注意すべきポイントについて詳しく解説します。
このページの目次
相続放棄の基本
相続放棄を行うと、その相続人は被相続人の財産も負債も一切相続しないことになります。相続放棄をした相続人は、はじめから相続人ではなかったものとみなされ、他の相続人にその分の相続権が移ります。
相続放棄が適用される主なケース
- 被相続人が多額の借金を残している場合
- 被相続人の負債の内容が明らかでない場合
- 他の相続人に遺産を全て譲りたい場合
相続放棄の手続き
相続放棄の手続きは、以下の流れで進めます。
1. 相続開始を確認
相続放棄の期限は、相続が開始したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内です。この期間内に手続きを行う必要があります。
- 期限内に行わない場合、相続を承認したとみなされることがあります(単純承認)。

2. 家庭裁判所への申し立て
相続放棄を希望する場合は、家庭裁判所に申し立てを行います。必要な書類は以下の通りです。
- 相続放棄申述書(家庭裁判所所定の用紙)
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続放棄する人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人の本人確認書類(運転免許証など)
申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

3. 家庭裁判所での審査
申し立て後、家庭裁判所が審査を行います。場合によっては、申し立て内容について確認するために、裁判所から質問があることもあります。
- 問題がなければ、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。

4. 相続放棄の効果発生
相続放棄が受理されると、その相続人は初めから相続人でなかったものとみなされます。
相続放棄の注意点とリスク
相続放棄にはメリットだけでなく、いくつかのリスクや注意点もあります。
1. 他の相続人への影響
相続放棄をすると、自分の相続権が次順位の相続人(例:兄弟姉妹、甥姪など)に移ります。そのため、次順位の相続人にも負債を引き継ぐ可能性があります。
- 特に負債が多い場合、次順位の相続人にも連絡をしておくとスムーズです。
2. 部分的な放棄はできない
相続放棄は、財産と負債の一部だけを放棄することはできません。すべてを放棄するか、すべてを引き継ぐかの選択となります。
3. 放棄の取り消しができない
相続放棄が一度受理されると、後から撤回することはできません。慎重に判断する必要があります。
4. 期限を過ぎると単純承認となる
相続放棄の期限(相続開始から3か月)を過ぎると、自動的に相続を承認したとみなされます。その後は負債も含めて相続する義務が発生します。
- 「熟慮期間の延長」を家庭裁判所に申し立てることで、3か月の期限を延長できる場合があります。
5. 相続放棄後でも負債を返済してしまうリスク
相続放棄をする前に、被相続人の借金を一部でも返済した場合、「借金を承認した」とみなされる可能性があります。
- 負債を引き継ぐ意志がなくても、軽率な行動は避けましょう。
特殊なケースへの対応
被相続人の財産が「負債だけ」とは限らない
被相続人の財産が負債だけでなく、不動産や現金などもある場合、相続放棄をする前に、財産全体の内容をしっかりと調査することが大切です。
- 財産調査を進める際には、弁護士や税理士など専門家の助けを借りると良いでしょう。
相続人全員が相続放棄した場合
相続人全員が相続放棄を行った場合、次順位の相続人(例:甥や姪)が相続権を持つことになります。それでも相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。
相続放棄を依頼するメリット
相続放棄の手続きや判断に迷った場合、弁護士に相談することで以下のようなメリットがあります。
- 法律の専門家が代理人として手続きを進めてくれるため、複雑な書類作成や裁判所とのやり取りがスムーズ。
- 財産調査や負債の内容確認をサポートしてもらえる。
- 次順位の相続人との連絡やトラブル防止を図れる。
当事務所のサポート内容
当事務所では、相続放棄を希望される方に対し、次のようなサービスを提供しています。
- 相続放棄の申し立て書類の作成代行
- 被相続人の財産調査(負債や財産の全体像を把握)
- 相続人間の調整や次順位相続人へのアドバイス
- 熟慮期間延長の申し立てサポート
相続放棄が必要かどうか迷われている場合でも、初回のご相談で状況に応じた最適なアドバイスを行います。