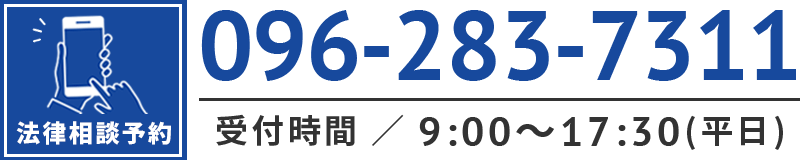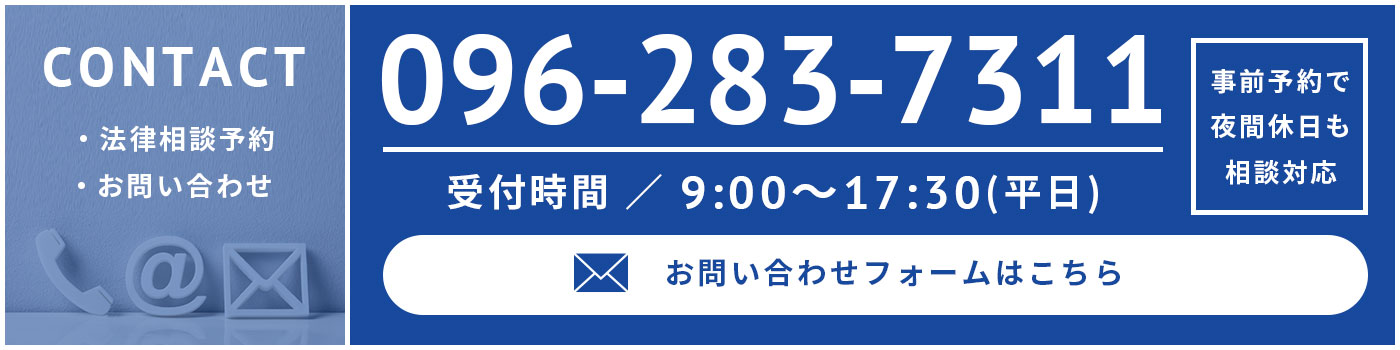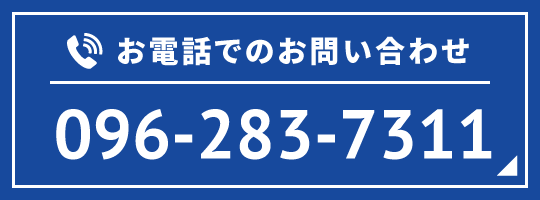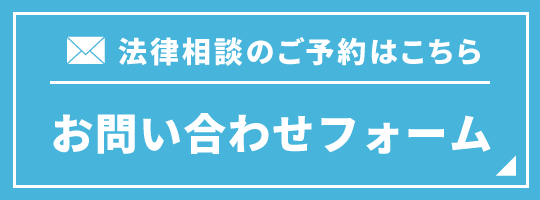遺産相続の手続きを進める際、誰が相続人になるのか、またどのように遺産を分けるべきかを知ることはとても重要です。民法では、相続人の範囲や遺産の分配割合(法定相続分)が明確に定められています。
本記事では、相続人の範囲と法定相続分について、わかりやすくご説明いたします。
このページの目次
相続人の範囲
相続人は、民法に基づいて以下の通り規定されています。
1. 常に相続人となる配偶者
被相続人(亡くなった方)の配偶者は、他の相続人の有無にかかわらず、必ず相続人となります。ただし、配偶者とは法律上婚姻関係にある方が対象であり、内縁の配偶者や事実婚の場合は相続権が認められません。
2. 血縁関係に基づく相続人
血縁関係のある相続人は以下の優先順位で決定されます。優先順位が高い人がいる場合、下位の人は相続人にはなりません。
第1順位:子(直系卑属)
被相続人の子が相続人になります。ここでいう子には、以下も含まれます。
- 婚姻関係にある配偶者との間に生まれた子
- 婚外子(法律上認知された場合)
- 養子(法的に養子縁組が成立している場合)
子がすでに亡くなっている場合、その子(孫)が代わりに相続することを代襲相続といいます。
第2順位:父母(直系尊属)
子がいない場合、父母が相続人となります。父母がすでに亡くなっている場合、祖父母が相続人となります。
第3順位:兄弟姉妹
子も父母もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(甥・姪)が代襲相続します。
法定相続分とは?
法定相続分とは、遺言書がない場合に、法律で定められた各相続人の遺産分配割合を指します。相続人の組み合わせによって法定相続分は異なります。
配偶者と他の相続人がいる場合
1. 偶者と子がいる場合
- 配偶者:1/2
- 子:1/2(子の人数で均等分割)
例:配偶者と子2人がいる場合 → 配偶者が1/2、子2人がそれぞれ1/4ずつ。
2. 配偶者と父母がいる場合
- 配偶者:2/3
- 父母:1/3(父母で均等分割)
例:配偶者と父母2人がいる場合 → 配偶者が2/3、父母2人がそれぞれ1/6ずつ。
3. 配偶者と兄弟姉妹がいる場合
- 配偶者:3/4
- 兄弟姉妹:1/4(兄弟姉妹で均等分割)
例:配偶者と兄弟姉妹3人がいる場合 → 配偶者が3/4、兄弟姉妹がそれぞれ1/12ずつ。
配偶者がいない場合
1.子のみがいる場合
- 子全員で遺産を均等分割。
例:子3人の場合 → 各子が1/3ずつ。
2. 父母のみがいる場合
- 父母全員で遺産を均等分割。
例:父母2人の場合 → 各父母が1/2ずつ。
3. 兄弟姉妹のみがいる場合
- 兄弟姉妹全員で遺産を均等分割。
例:兄弟姉妹4人の場合 → 各兄弟姉妹が1/4ずつ。
※ただし、半血兄弟姉妹(父または母が異なる兄弟姉妹)の場合は、全血兄弟姉妹の半分の割合となります。
特別な相続分の調整
遺産分割の際、以下のような事情がある場合には、法定相続分が調整されることがあります。
寄与分
相続人の中で特に被相続人の財産形成や介護に貢献した人がいる場合、その相続人の相続分が増えることがあります。
特別受益
生前贈与や結婚・住宅購入資金の援助などで特別な利益を受けた相続人がいる場合、遺産全体からその分を差し引いて分割する場合があります。
法定相続分に基づく円満な遺産分割のために
法定相続分は、あくまで遺産分配の目安であり、相続人全員が合意すれば、自由に分割方法を決めることができます。しかし、家族間で意見がまとまらずトラブルに発展するケースも少なくありません。
当事務所では、相続人間の意見調整や遺産分割協議書の作成など、円満な遺産相続を実現するためのお手伝いを行っています。法定相続分の考え方やご自身のケースに応じた適切な分配方法について、ぜひご相談ください。